


全国プログラムへの参加が
挑戦的な進路選択のきっかけに



全国プログラムへの参加が
挑戦的な進路選択のきっかけに
「アントレ教育を受けてなければ、無難な進路を選んでいたかもしれない」。そう話すのは、昨年まで山口大学に在籍していた京面裕也さんです。大学時代に参加した全国アントレプレナーシップ人材育成プログラム(以下、「全国プログラム」)での経験が、京面さんの進路選択に大きな影響を与えました。現在は社会人1年目。山口県内の企業で働く京面さんに、学生時代に体験したアントレ教育について伺いました。
今年の3月に山口大学を卒業し、現在は、山口県で一般廃棄物や産業廃棄物の回収・処理事業を行う、株式会社中特ホールディングスで働いています。弊社は少し変わっていて、個性的な新規事業に積極的に取り組んでいます。例えば、英語で行うプログラミング教室の運営や、ダチョウの抗体を使った花粉症対策用「のど飴」の製造など、「廃棄物の会社」という枠にとらわれない事業を展開しています。このようなチャレンジングな姿勢に惹かれ、入社を決めました。まだ入社1年目の新入社員ですので、まずは一つずつ仕事を覚えていかなければいけませんが、将来的には私も新規事業を起ち上げることを目標にしています。

高校までは広島県で暮らしていて、山口大学への進学を機に地元を離れました。県外に出たのは、自分の価値観の幅を広げたかったから。なかでも山口大学を選んだ理由はいくつかあります。高校時代から英語が好きで、進学した国際総合科学部には1年間の留学制度が整備されていました。また、カリキュラムの特色として英語教育に加え、リベラルアーツを取り入れており、幅広い分野を学ぶことができる点も魅力でした。
アントレプレナーシップに興味を持ったのは、高校時代です。当時、影響を受けた本の著者の多くが経営者であり、彼らの主体的に生きる価値観に共感したんですね。私も彼らのようになりたいと思ったのが、アントレプレナーシップへの入り口でした。
実際にアントレ教育に触れたのは、大学1年生のときに受けた授業が最初です。リーンキャンバスという、スタートアップや新規事業の立ち上げに使用されるツールや、ビジネスにおけるインタビュー手法を学びました。しかし、当時はちょうどコロナ禍で、インタビューもオンラインだけ。授業自体も1カ月の短期プログラムだったため、消化不良というか、何かもどかしさが残ったんです。
その後、週末の3日間で起業体験ができるイベント「スタートアップウィークエンド(※)」に参加しました。そこでの体験は非常に印象的でした。自分が考えた事業アイデアについてインタビューを行ったり、MVP(Minimum Viable Product)を作成して起業家の方にプレゼンするなど、座学とは全く異なる実践的な体験ができました。参加者も同世代だけでなく、上は70代から下は中学生まで、幅広い世代から集まっており、非常に新鮮な経験でした。

大学2年生のときには、念願の海外留学を果たしました。行先はドイツです。経営学とデザインを学べる大学に進学しました。食事も街の風景も人種も文化も何もかもが日本とは違い、周りにはアジア人すらほとんどいない環境は、本当に刺激的でした。また、ドイツでもスタートアップウィークエンドに参加したのですが、非常にハイレベルでした。起業家や投資家も参加していて、学生のレベルも本当に高かった。参加者の多くがプログラミングやデザインなど、何かしらの技術を持っていました。なかにはアプリを開発してきたり、実際にプロトタイプを作成してきた学生もいました。英語でのプレゼンテーションも流暢で、非常に刺激を受けると同時に、自分の未熟さを痛感しました。

帰国後はドイツで学んだことを山口でどう生かせるのかを考え、創業支援施設を活用して、週末にドイツ料理を提供するお店を出店しました。スタートアップウィークエンドのようなイベントだけでなく、自分が主体的に動けるかを試したかったからです。自分の実力を測るためにも、お客さんの反応を見たかったという思いもありました。ドイツのクリスマスマーケットの雰囲気を感じられる料理を提供するなど工夫しましたが、利益はそれほど上がらず、自分の実力を思い知らされました。それでも、お店を経営するなかでの試行錯誤や、売上と向き合う日々は、自分にとってかけがえのない経験となりました。

大学3年生の年末に、全国プログラムに参加しました。ちょうどドイツ料理店を始めたばかりのころで、学び直しをしたい、自分と同じようにお店や事業を既に始めている人たちがいれば話を聞きたいと思い、参加を決めました。当時はコロナ禍のためオンラインでの開催でしたが、特に印象に残ったのは顧客インタビューのやり方です。それまでは自己流で、抽象的な質問が多かったり、手順を把握していなかったため、ドイツ料理店を始める際に行ったインタビューでも、あまり良い情報が得られませんでした。しかし、このプログラムで学んだことを山口に戻ってから実践し、自分のお店作りに少しでも役立てることができたのは良い経験でした。

その後、大学4年生のときに2年連続で全国プログラムに参加しました。コロナ禍も収束し、対面での開催となったため、より熱量の高いプログラムになるだろうと期待していました。それに、対面での開催は仲間を作りやすいだろうし、全国各地から同世代の人々が集まる良い機会だと思ったからです。
プログラムの内容は、仮説検証や顧客インタビュー、プロトタイプ開発といった実践的なワークショップ形式でした。驚いたのは参加者のレベルの高さ。仮説検証の精度が高く、顧客の課題に対する解像度も非常に高かったです。プレゼンテーションもスライドを駆使して見事にまとめていました。私のチームは4人で、私以外のメンバーはすべて東京からの参加者でした。異なるバックグラウンドを持つメンバーとの意見交換を通じて、最終的に成果物を完成させるまでのプロセスは、チームワークの重要性を改めて実感させてくれる貴重な経験となりました。
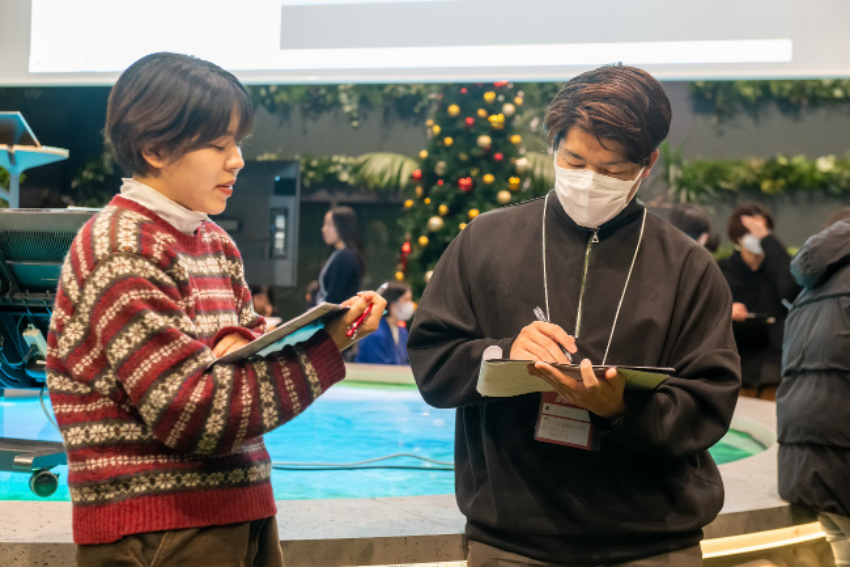
全国に仲間ができたことも大きな収穫でした。プログラム終了後も70人ほどがつながり、今でも「こういうことをやっているのですが、興味のある方はいませんか」といったやり取りが続いています。実際に、岡山から参加した高校生がクラウドファンディングを行っており、私もそのサポートをさせていただきました。頑張っている同世代との横のつながりは、私にとって大きな刺激になりました。「自分は山口県のなかでは、ようやっとるほうでしょ」と思っていたところもあったのですが、全国規模で見ると「めちゃめちゃすごい人たちがいる」と痛感させられました。全国プログラムは、自分を測る一つの基準となりました。
全国プログラムでの経験は、その後のキャリア選択にも少なからぬ影響を与えました。もし参加をしていなければ、無難な選択をしていたかもしれません。実はそのころ、ドイツ料理店を経営する一方で、「いったん地に足をつけて考えたほうがいいのではないか」といった考えも持っていました。しかし、このプログラムでの経験が、挑戦的な人生を歩むための勇気を与えてくれました。
アントレプレナーシップ教育は、行動のきっかけを与えてくれます。全国プログラムでも、講師の馬田隆明先生が「行動」の重要性を強調されていました。新しい事業を作ろうと頭で考えたところで、行動しないことには何も始まりません。もし全国プログラムに少しでも興味があるなら、ぜひ参加してみてください。あの熱量と情報量を体感してほしいです。特に地方にいる学生の方にとっては、全国から同じ志を持った仲間が集まるまたとない機会です。既に地域のコミュニティで活動している学生の方も多いでしょう。そこでは応援してくれる大人がたくさんいるかもしれませんが、その環境に満足せず、全国プログラムに参加して自分の視野をさらに広げてほしいと思います。
