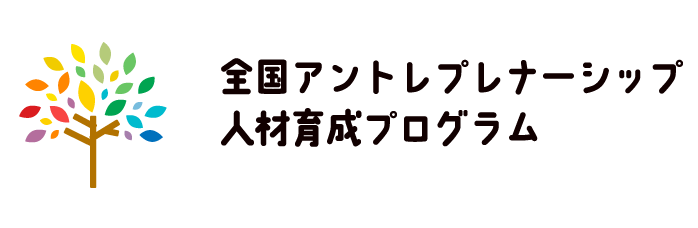

※本編は、イベントの前半に行われた講義を中心にまとめております。後編であるピッチ・ワークショップ・交流会もぜひご覧ください。
↓後編はこちら
2024年7月6日(土)、Tokyo Innovation Base(TIB)にて、全国アントレプレナーシップ醸成促進事業の一環として、学生交流イベントをハイブリッド形式で開催しました。本イベントには、全国からの大学生・大学院生・高校生のみならず、民間企業や教職員、計60名弱が参加し、講演・ワークショップを通じて、キャリア・アントレプレナーシップに関する知識やスキルを深める機会となりました。
講師には、東京大学FoundX ディレクターの馬田隆明先生をお迎えし、「キャリア・アントレプレナーシップ」をテーマに講義が行われました。講義では、キャリアデザインにアントレプレナーシップを活かす方法について解説され、参加者は自律的なキャリア構築の重要性を学び、新たな知識やスキルを身につけ、自律的なキャリア構築のための第一歩を踏み出しました。
【講師プロフィール】
東京大学FoundX ディレクター
馬田隆明
東京大学でスタートアップ支援ならびにアントレプレナーシップ教育を担当。
University of Toronto 卒業後、日本マイクロソフトを経て、2016年から東京大学。東京大学では本郷テックガレージの立ち上げと運営を行い、2019年からFoundXディレクターとしてスタートアップの支援とアントレプレナーシップ教育に従事する。スタートアップ向けのスライド、ブログ等で情報提供を行っている。
著書に『逆説のスタートアップ思考』『成功する起業家は居場所を選ぶ』『未来を実装する』等
文部科学省・学術政策局 産業連携・地域振興課 産業連携推進室 室長補佐 大榊 直樹氏より、開会の挨拶を行いました。本日のイベントを全力で楽しみ、アントレプレナーシップを身につけること、また参加者同士で交流を深めていただくことや文部科学省のイベントや他のアントレプレナーシップイベント等への参加など、期待と激励の言葉が贈られました。

馬田隆明先生による講義では、自律的なキャリア構築の方法の解説があり、参加者は、自身のキャリア形成におけるアントレプレナーシップの役割について学びました。

<講義内容抜粋>
2023年12月23日(土)、24日(日) 全国アントレプレナーシップ人材育成プログラムの振り返り
昨年12月に学んでいただいた内容を振り返りますと、起業家(アントレプレナー)≠起業家性(アントレプレナーシップ)ということや、新しい事業を起こすことと会社を起こすことは少し異なるということ等をお伝えしました。
皆さん個々人にとっての事業は、ある意味で、皆さん自身の「キャリアを作ること」であると思っています。前回学んだアントレプレナーシップが、皆さんのキャリアという事業を起こしていくために、どう使えるかという話を今回はしていければと思います。
前回、アントレプレナーシップには、機会・資源・行動という3つの要素があることを話しました。前回はこの中でも「行動」に軸を置いていましたが、今回は機会に重点を置いてお話しできればと思います。
Will・Can・Must
日本でよく使われるキャリア形成のフレームワークとしてWill・Can・Mustがあります。これらの交わる部分が目指すべきキャリアとして示されていたりします。
ここで、皆さんもみたことあるかもしれませんが、スティーブ・ジョブズの動画を紹介します。
〜スティーブ・ジョブズの動画〜
ジョブズも自分の好きなことを探さなければいけないと言っていますね。キャリアを考えるときには、やりたいこと、つまりはWillを決めるところから始めようとする人が多いのではないかと感じています。
では、皆さんが今考えている「自分のやりたいこと」というのはどのくらいやりたいことですか?
【挙手率】
0%:なし
20%:少なめ
40%:少なめ
60%:ボリューム層
80%:多め
100%:数人
100%の自信を持って自分のやりたいことがあると言える人は数人ですね。みなさん60%ぐらい。これは普通の学生の方々よりも比較的高いと思います。私の経験からすると、多くの学生の皆さんは「自分のやりたいこと」を持てていないですし、持てていないことに不安を感じている人も多い。
実際、大学の講義で起業家を呼んでお話してもらったあとに、学生の皆さんから質問を取ると、ほぼ毎年「やりたいことが見つからないのですがどうすれば良いですか?」という質問がたくさん出ます。
世の中の風潮として、「やりたいことがあること」が求められますが、実際はやりたいことがある人はそう多いわけでもないから、不安になったり、そういう質問をする人が多いのかなと思います。
なので、本日は「やりたいこと」がない人や「やりたいこと」に自信がない人、これから「やりたいこと」を考える人向けにお話をしたいと思います。
まず結論として、「やりたいこと」がない人に対して個人的にお勧めしているのは、Willを後回しで考えることです。例えば、社会的要請であるMustから始めて、徐々にWillやCanを見つけていくのが良いと思っています。
Canから始める罠
今自分ができること、つまりCanから始めようとすると、自分のできる範囲でWillを探してしまいます。でもそれは、広大な暗闇の中で、ぽつんと明かりのあるところだけを探しているようなものです。自分では見えていない範囲にWillがあったときには、見つけることができません。
でもよく考えてみてください。現在から過去を振り返ると、自分の「できること」というのはこの10年でずいぶんと増えてきたはずですよね。だったら、今後自分のできることも増えていくはずです。
だから、今自分が持っている強みだけに注目してキャリアについて考えるのは避けたほうが良いでしょう。今はできないことも、将来できるようになります。できるようになっていけばいいのです。
それに自分のCanだけでなく、たくさんの人のCanを集めて、チームとしてできることを増やすのも一つの方法です。そうすれば、自分のCanの範囲だけで、やりたいことを探さなくても良くなります。
Willから始める罠
Willにも同じことが言えます。今自分が見えているWillは、広大な暗闇の中にある、ぽつんとした明かりのあるところで探しているだけかもしれません。
今自分が持っている経験の中でやりたいことというWillを決めるのは、ある意味、積極的に過去に縛られようとすることだとも言えます。でも、過去に縛られて未来を決めるというのは勿体無いです。
一方で、未来だけで今の自分を定めるのも勿体無い。「未来にこういうキャリアを歩みたいから」と、そこにまっすぐ向かっていくと、他のものが見えなくなって、自分に向いていた別のことを試せないかもしれないからです。
だから、自分の小さな好奇心という仮説を持つことが大事だと思います。皆さんの起業のアイデアが仮説であるように、皆さんのWillも仮説です。それを仮説検証していけば、Willを徐々に見つけていくことができます。
仮説検証の失敗というのは、間違うことではなく、学びが少ないことです。学んだ結果、自分のWillが間違っていたことに気づくのは、失敗ではありません。そうした経験を経て、自分のWillを変えてみるのは大きな学びを得たということです。
それと、自分のWillを育てていくという発想も大事です。愛は育てていくことはできると「愛するということ」という著書の中でも触れられています。はじめは小さな好奇心というWillでも、それを育てていく、少しずつ伸ばしていくことはできるのです。
私の周りの起業家でも、自分の最初のWillが小さくても、事業に取り組んでいくうちにWillが大きくなっていって、Will・Can・Mustの重なりが増えていくといったことがよくあります。みなさんのWillが後から育っていく可能性を信じてください。
芯のある自分、しっかりとした自分がよいと言われがちです。でもむしろ、若い頃は自分自身のアイデンティティを柔らかく持つことも重要です。「自分はこういう人間だ」と決めてしまうのはもったいない。皆さんは変わることができるし、成長することができるからです。どうしてもやりたくないことはしなくて良いと思いますが、しっかりとした自分を大切にしながら、同時に柔らかい自分という両面を持つことが大事です。
Mustから考えた方が良い
Canは変えられます。Willは育てられます。でもMustという社会的な要請は自分の力で最も動かしづらいものです。だから、ここを出発点にすると効率的です。
また、Must と Canの重なる部分は、金銭的な報酬を得やすい領域です。金銭的な報酬があるということは、継続的に行動できるということです。その結果、Willを育てることもやりやすくなるでしょう。
Mustの領域は成長の機会が降ってきやすいという特徴もあります。社会的にやるべきことには、多くの仕事が生み出されます。最初は偉い人たちがその仕事をしますが、次第に溢れて、下に落ちてくるからです。Mustから始めるというのは、機会から始めるということでもあります。機会というものはしばしばMustとCanの間にあります。やるべきだけれども、他人がやっていなくて、自分ができることを見つければ、お金を稼ぐことが簡単になります。
自分よりもCanの大きな人が、大きなMustの仕事を取って行くと思われるかもしれません。確かに社会全体で見たときはそうでしょう。でもキャリアはもう少し限定的な社会の中で作られていきます。社会全体では自分よりできる人がたくさんいるとしても、あなたが所属する企業やコミュニティの中で、あなた自身が一番であれば、その企業やコミュニティという小さな社会の中では、あなたは貴重な存在となり、仕事が回ってきます。それはあなたのキャリアの機会となるでしょう。
重要なのがポジションです。いつ、どこに自分の位置を取るかです。もしくは、どこで戦うかとも言えます。ポジションが多くの成果を決めます。大学生や高校生になるまでは、受験やテスト等、全員が同じ試験で評価される競争の場が用意されていました。でも社会では、どこで戦うかという選択自体が非常に重要になります。
たとえば起業でも、業界全体が成長している等、機会の多い場所で起業すると成功しやすいと言われています。一方、どんなに優秀な起業家でも、市場が縮小していく中で大成功するのは難しいとも言われます。つまり、どんなに優秀な努力家でも、どこで努力するかが、その努力の価値を決めてしまうのです。業界や組織全体が成長している場所、機会が落ちてくる場所、比較的混んでいない場所を意識したポジション取りをすることで、ちょっとした努力でも高く評価されることはしばしばあります。そうした場所を探すためにも、アントレプレーシップを活かしていきましょう。ただし、短期的な穴場になっているような機会を探すよりも、長期的に成長できるような場所に身を置くことをお勧めします。
キャリアにおいては立場も重要になります。難しい課題に挑んでいるアントレプレナー等は希少な存在なので、いろんな場所で講師等として呼ばれています。言い換えると、環境(場所×立場)が人を作るということです。私自身、自分が優秀だったというよりも、自分が幸いにして良い環境に身を置けたから、成長の機会をいただけたと感じています。
リスクをとって決める
起業をすることも、キャリアを選ぶことも、怖いことです。でも決めなければ前に進めません。そしてもし決めたら、仮説を正解にする、というマインドがあればアントレプレナーシップを活かせると思います。
まとめ
すでにやりたいことがある人は素晴らしいです。そうでない人は、Must→Will→Canの順番で考えてみましょう。そして行動しながら学びましょう。最後は決めましょう。
本日は12月に学んだアントレプレナーシップの考え方はキャリアにも活かせるということをお伝えさせていただきました。ありがとうございました。